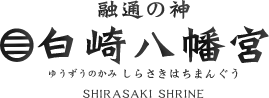だるまは、インドから中国に仏教を伝えたお坊さまの達磨大師(だるまたいし)がもとになった縁起物です。達磨大師の徳の高さ、そしてありがたい教えを大切にした人びとによって、座禅の姿をモチーフにした「だるま」が生まれました。
だるまのデザインには多くの願いが込められています。たとえば赤色の塗装は魔除けや運勢を高めるとされ、倒れても起き上がる、七転び八起きの姿は「無病息災」や「家内安全」の縁起に通じています。願いをかけながら片目を入れ、願いが成就したら残りの目を入れるというのも、広く親しまれている風習です。
だるまはそうやって長い間、私たちの開運招福や大願成就、商売繁盛などさまざまな願いに寄り添ってきた、とても馴染みのある存在なのです。
幸せをもたらす
心願成就の福だるま

だるまの歴史
だるまの目入れ作法

だるまの目入れは開眼(かいげん)といい、心の目がひらいたことを表現します。目を入れることで、より一層ご自身や家族をやさしく見守ってくださります。目入れの順番は、一般的にだるまの左目(向かって右側の目)から入れるのが習わしとなっています。
合格祈願や必勝祈願などでだるまに願かけをする場合、はじめにだるまの左目に目入れをし、願いが叶ったら右目を入れましょう。
なお、魔除けの縁起物として飾っていただく場合は、先に両目に黒目を入れてから飾るのが一般的です。
願いが叶った次の年は だるまを大きくします

だるまの置物には様々なサイズがありますが、それには理由があります。
地域によっては、はじめは小さなサイズのだるまを飾り、健康や商売繁盛などを祈願します。そして願いが成就し開眼させた次の年は、だるまをひと回り大きくして、さらなる飛躍を願うのです。もし願いが成就しなかった場合には、同じ大きさのだるまでもう一度願かけを行うとよいとされています。だるまが大きくなりすぎた時や初心に返りたい時には、小さなだるまからまた飾ります。
安置されただるまは、日々、皆さまの心からの願いに寄り添ってくれることでしょう。
ご神徳を祈願した 白崎八幡宮の福だるま

白崎八幡宮のだるまは、大神様のご神徳(ご利益)を入魂した特別なだるまです。
魔除け・病除け・商売繁盛・合格祈願など、あらゆる願いを受け止めます。運気を高めるだけでなく、目標を達成するために前向きな向上心も高めると言われています。ご自宅の神棚や勉強机などに飾っていただいたり、ストラップとして常に身につけていただくことをおすすめしています。
だるまのご利益期間は1年間と言われており、節目を迎えたら感謝しながら供養し、新しく購入して願いをかけると良いとされています。お役目を終えただるまは、小物供養でお納めください。
スペシャルコンテンツ
白崎八幡宮がお届けする、神道にまつわる情報や豆知識を掲載したページです。
自宅での神棚の祀り方やお朔日参りについてなどの神社に関する情報はもちろん、ネット祈願の方法や良縁につながる縁切り祈願の紹介など、白崎八幡宮独自の豆知識も載せています。